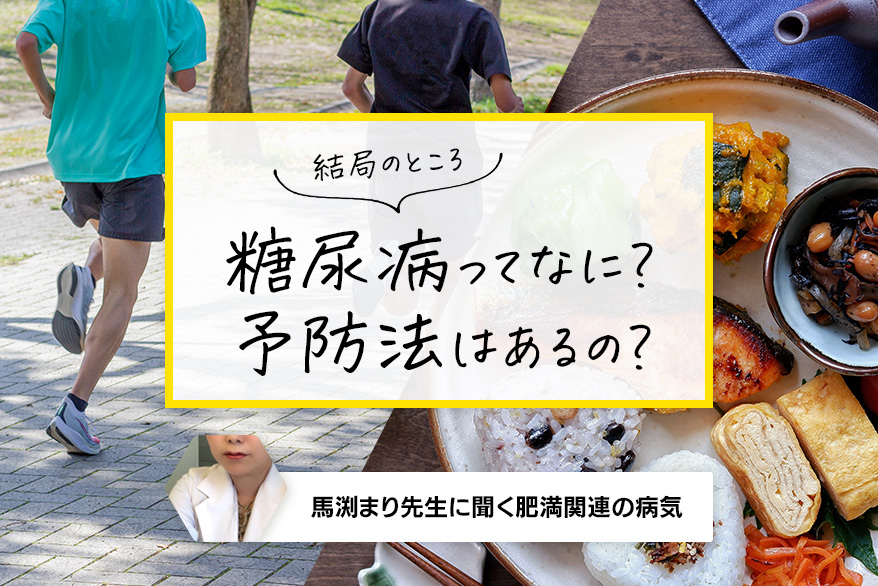
こんにちは!食べるの大好き、ぽっちゃり男子大好きな内科医、馬渕まりです。澄み切った青空と涼しい風。秋がやってまいりました。秋といえば食欲の秋ですが、ヒトは冬眠しないのであまり脂肪を蓄えないように気を付けましょう。
さて、今回は肥満に合併しやすい病気の話その1です。太った人がかかりやすい病気と聞いてまず想像するのは「糖尿病」ではないでしょうか。これは半分あたりで、半分ハズレです。生活習慣という言葉があるために肥満や、過食、運動不足など「生活習慣が悪い」とかかる病気と思われるかもしれませんが、実は糖尿病になりやすい体質+肥満、ストレスなど様々な環境要因で発症します。生活習慣だけではないですので、ご自身を責めたり、糖尿病の方を悪く言ってはいけません。今回の一番大事なポイントはここですよ。
言いたいことを言って満足しましたが、ここで終わると糖尿病って結局何なの?なんで肥満と関係があるの?病名は知っているけど症状知らないし?予防方法はあるの?と疑問符だらけになると思います。安心してくださいキチンと説明いたします。
まず糖尿病の概念からはじめましょう。教科書を開くと「糖尿病とはインスリンの作用不足に基づく慢性の高血糖状態を主徴とする代謝疾患群である。」と書いてあります。ちょっとわかりにくいですね。言い換えますと「インスリンというホルモンの作用が悪くなって、そのために血糖値(血液中に含まれるブドウ糖)が慢性的に高くなり、それによっていろいろ不都合なことが起きる病気」となります。少しわかりやすくなったでしょうか?続いて出てきた用語の説明です。
みなさま、本日は何を食べましたか?私は昼に米飯と豚野菜炒め、みそ汁とクリームコロッケです。今あげたメニューのうち、主食にあたるのが米飯です。米、パン、うどんなど主食は炭水化物がメインです。炭水化物は糖がたくさんくっついてできており、消化されるとブドウ糖に分解され、身体のエネルギー源として使うために血液中に吸収され各細胞に分配されます。このブドウ糖が血液中にどのくらいの量あるかが血糖値で通常は狭い範囲で一定しています。
インスリンと聞くと糖尿病の人が使う注射薬を想像しませんか?実はインスリンは身体の中にあるホルモンなのですが、糖尿病の人はインスリンの作用が足りないから外から注射で補っているのです。インスリンはすい臓で作られ、食事の刺激や食後にブドウ糖が腸から吸収され血糖値が上がると、それに反応して分泌されブドウ糖を細胞の中に引き込みます。つまりインスリンが正常に作用していれば、血中のブドウ糖はすぐ細胞の中に入りますので高血糖にならないわけです。これの機序が破綻したのが糖尿病です。ちなみにインスリンの工場であるすい臓がダメージを受けた場合も糖尿病になる場合があります。
風邪をひくと熱が上がったり咳が出ますよね。糖尿病になると…初期の自覚症状はあまりありません。極端に高血糖になった場合は喉が渇いたり、疲れやすくなったり、ものすごくひどいと意識がなくなる等の急性症状がでることもあります。が、初診で来られる方をみますと、症状はないのに「健康診断で指摘された」、「他の病気で血液検査をしたらたまたま見つかったと」いう方がほとんどです。
自覚症状がないなら放っておいても…と思われるかもしれませんが、慢性的な高血糖は身体、特に血管にダメージを与えます。高血糖が血管を傷める機序は結構ややこしくてそれだけで1回記事になる量&読んでもあまり面白くないと思いますので割愛いたしますが、血管を砂糖漬けにすると傷むよねくらいに認識しておいてください。
比較的大きな血管がダメになると心血管の病気や脳梗塞をおこしやすくなります。糖尿病があるだけで心臓の血管が詰まったり狭くなる病気の発症頻度は2.5倍に、脳梗塞を起こすリスクも2~3倍になります。ここに肥満や喫煙、高血圧が加わると掛け算ですのでお気を付けください。
微小血管が慢性的な高血糖でダメージを受けると、糖尿病に特有の合併症を起こします。中でも3大合併症と呼ばれるのが神経障害、網膜症、腎症です。糖尿病性神経障害は持続する高血糖により神経周囲の血管だけでなく、神経そのものの性質が変わってします。神経障害は主に2つに分けられ、自律神経が障害されると立ち眩みや胃腸障害、下痢、便秘、勃起障害があらわれることもあります。
末梢神経が障害されると足のしびれや感覚低下、こむらがえりなどが生じます。糖尿病性神経障害は足先や、足裏から起こりやすいと言われています。感覚の低下は足のケガの見落としや軽視につながり、気が付いた時には傷が深くなり、悪化して足を切断する方もおられます。
眼の中の微小血管が障害されるのが糖尿病性網膜症です。網膜症が進むと、眼底出血をおこしたり失明をすることもあります。我が国の中途失明原因の3位(以前は1位でした)が糖尿病性網膜症です。
腎臓は血液から尿を作るため微小な血管が集まっています。ここが障害されると、最後には尿がつくれない、つまり体の中の余分な水分、塩分、電解質や老廃物を体外に排出できなくなります。そうなると死んでしまいますので、現在は機械などで腎臓のかわりをしてもらう「透析」を行いますが、血液透析であれば週3回数時間の治療が必要で、水分の摂取も制限する必要がでてきます。
怖い話をたくさん書きましたが、これらの合併症は高血糖が長く続くと起きてきます。裏をかえせば糖尿病であっても、血糖値を正常に近くできれば糖尿病のない方とほぼ変わらないことになります。そのためには早期からの治療(食事、運動が基本で、不十分な場合は薬を使います)が大切です。健診などで指摘された場合は早めに受診してくださいね。
イエス、高須クリニックです!デンマークの研究になりますが、肥満の人は標準体型の人に比べて2型糖尿病(※)の発症リスクが5.8倍に上昇していました。これは遺伝要因を含めたほかのリスク要素よりきわめて高く、肥満のリスクが浮き彫りになりました。また若いうちから太っている人ほど糖尿病になりやすいというデータもあります。
肥満で糖尿病のリスクが上がる原因は前回も触れた「内臓脂肪」にあります。肥大した脂肪細胞からはインスリンの効きが悪くなる物質がたくさん放出され、逆にインスリンの効きをよくする物質の出が悪くなります。この結果、インスリンが出ていてもあまり効かない状態になり、糖尿病になります。また、インスリンが効きにくいために、すい臓ががんばってインスリンをたくさん出し続ける状態が続くと、すい臓が弱った状態になりインスリンの分泌が落ち、ますます高血糖になるという悪循環に陥ってしまします。
※2型糖尿病:糖尿病の9割がこのタイプ。遺伝要因+さまざまな環境要因で発症する。一般的にいわれる糖尿病がこちら。これに対して若年発症が多い1型糖尿病はインスリンを作るすい臓の細胞が破壊されることで起こる糖尿病で最終的にインスリン注射が必須になるタイプ。
もちろんあります。詳しくは馬渕まりの有料サロンへ…嘘です(サロン自体ありませんので探さないでください。)書くと地味ですが、まず食事です。バランスの良い食事、食物繊維の多い食事にしてよく噛みゆっくり食べる。そして運動。1日30分から60分の有酸素運動がおススメですが、まずはできる範囲で。細切れででもゼロよりはずっと良いです。
肥満がある方、おそらくこのサイトを読んでいる方はLサイズ以上が多いと思うので強調します。『痩せるの大事』。5%の体重減少と運動習慣で、耐糖能障害(糖尿病の一歩手前)から糖尿病への進行を3年間で52%減少されたという報告があります。
あとは禁煙。煙草を吸うと糖尿病になるリスクが1.37倍になります。加えて喫煙は動脈硬化の危険因子です。禁煙をすると、体重増加を伴うことが多く一時的には発症リスクが高まりますが、長期で見ると低下します。
さて、ここからは編集部からの質問に答えるコーナーです。
血糖値が少し上がったくらいでは自覚症状は出ません。一歩手前で気づくコツは健康診断を受けることです。
糖尿病は「体質」の病気なので治癒することはありません。
しかし、肥満の方に多い、インスリンは出ているけれども効きが悪いタイプの方は減量、食事療法、運動療法で血糖値が正常になることはよくあります。ただし、血糖値が上がりやすい体質は変わっていませんので、ここで暴飲暴食を続けてしまうと再び血糖値は上がってしまいます。
美味しいものは一生禁止?いえいえ、糖尿病の方が食べていけない食品はありません(菓子パンやジュースなどとりすぎない方が良い食品はあります)。量やタイミングを考えれば大丈夫です。誕生日などイベントの際はいつもより食事制限をゆるめて、前後の日で帳尻を合わせれば良いくらいの気持ちでいきましょう。
糖尿病で尿に糖が漏れ出すのは、血糖値が、およそ170mg/dL以上になってから。初期段階では尿糖がでないこともあります。1日20-30gの糖が尿に出る状態になれば甘味はする計算です。尿から甘いにおいがしたので受診したという方も少数ですがいらっしゃいます。
糖尿病は「体質」の病気だったんですね。そして、早めに気づくにはやっぱり健康診断!食生活に気をつけることと運動ですね。スポーツの秋ということで運動を始めるにはちょうど良い季節になりましたので、皆さんも体を動かしてみては?
次回もお楽しみに!